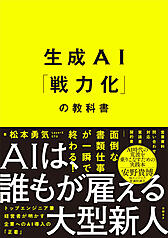13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ アクセス解析も「型」を覚え、準備に頭を使おう
メディア・リサーチの世界を20年やってきましたが、例えばアンケート調査などでは、頭を使う仕事の9割が調査設計などの準備に占める部分だと思っています。
何の目的でやるのか、どういう仮説を検証したいと思っているのか、そのためには誰に聞くのか、ではどうやってその人達を抽出するのか、仮説を検証するための質問文は、回答の選択肢は、集計時に必要な補助的質問はどのようなものを用意しておくべきか。などなど
もちろんアンケート調査の準備から報告までの全行程では、印刷したり、調査票を発送したり(郵送法なら)、集計作業をしたり、レポートを書いたり様々な作業があって、それぞれに時間を取られ、ミスしないように精神的に休まることはありませんが、そこは流れ作業的な事が多く、あまり「頭を使う」ことはありません。
特に最初の準備をしっかりしていれば、各段階で想定されるトラブルなどに対しても冷静に対応することができます。準備万端なら起きるトラブルは殆ど想定できます。
最近はアンケート調査もインターネット調査で自分自身で安くできるサービスが増えてきましたが、プロに設計を頼まないで素人が見よう見まねで実施して、質の低い調査も多くなっているのではないかと想像しています。基本的な「型」があるので、自分でやるにしても一度プロに学んでおくべきだと思います。基礎と重要なポイントがどこかを理解しておけば、応用はできますので。
アクセス解析も同じで、中規模以下のサイトであれば、無料のGoogle アナリティクスで十分という世界になってきています。しかし「型」を知らないで拙速に始めてしまうと、各所で躓いてしまいます。
有料ツールであれば、何かあってもさらにお金を出せば、ベンダーか代理店がコンサルにも応じてくれるし、お任せもできますが、無料のツールですと自己解決しなければなりません。
どのツールでも、それぞれのツールに応じた初期設定などがあります。データを収集する以前に設定しておくべきものから、集計時までに設定しておけばよいものなど様々ですが、そのツールの力を最大限に引き出すには、それぞれの準備に「頭を使う」ことをお勧めします。
手軽に始められるGoogle アナリティクスは、サポートがないからこそ、自分で「型」を覚え、その型に則って準備に頭を使うことが大事です。

noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ 継続性のないデータをトレンドデータとして繋いではいけない
久々にデータに関わる騒動がありました。短い時間でしたが Yahoo!Japanのトピックスでも「mixi「ユーザー激減」に反論」と題して掲載されていました。
詳細は説明しないので、検索などで全貌は掴んで頂きたいのですが、簡単に言うと、月次でリリースされる調査会社のデータをグラフにして毎月ブログに載せている著名な方の投稿がきっかけです。
その月の更新データでは、あるサイトの利用者数の集計方法の定義が変わりました。投稿の中では、それについても詳細に補足説明がなされているのですが、折れ線グラフは過去データと継続性があるように実線で結ばれていました。
悪いことに、定義変更でそのサイトの利用者数は、過去の定義での集計数字と比較すると結構落ち込んでいました。その数字の見掛け上の下落を受けてか、「そのサイト終った」的な、そのサイトやサービスに対する批判のような、本質から外れた書きこみも増えました。
今回その対象になったサイトが大手のメディアサイトだったため、その投稿から派生してネット上を流れはじめたクチコミが、メディア、広告系の多くの人の目に留まった可能性があります。そのブログ自体もソーシャル系で著名な方なので影響は大きかったでしょう。
今回のような場合に、過去データも含めてどのようなグラフを書いたら良いかということですが、自分で昔書いたブログの記事をご参考になって頂ければと思います。
http://ibukuro.blogspot.com/2010/02/blog-post_22.html
これは電通が毎年発表する日本の広告費の媒体別の統計ですが、途中の年から定義変更があり、2005年を境にインターネット広告の経年比較ができなくなったのですが、そこだけ点線にして、さらにグラフ中にも、「基準変更のため前後で単純比較できません」的な記述を付けました。
もちろんこれで完璧だという積りはありません。二つ目のグラフは棒グラフですが、注意書きはしているものの、グラフでの表現を諦めています。
今回の件は何かきっかけがあったら、それをキャッチーな話題にする、単なる悪口を書きこむ機会にしてしまうといった周辺の人の行為が問題だと思いますが、自分が作ったデータやグラフが、別の悪意をもった意見のきっかけにされる隙を少なくする注意は必要だと感じました。
逆に言えば、私が毎日のようにTwitterで呟いていることですが、意図を持って数字やグラフを作るという方法もあります。でもそれはなるべく社内でお使い頂ければと思います。数字やグラフは一人歩きするのですから。

noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
SQとは Social Quotient のことで、知能指数のIQをもじったものだ。幸福度を高めるような他者へのかかわりの力を「SQ」という指数で表現することにしたらしい。で、SQが高い人は幸福な人であるという結論。しかしそもそも「幸福度を高めるような他者へのかかわり」という言葉自体から考えて、「SQが高い人は幸福な人である」は同義なのではないか、単なる言葉の言い換えとしか取れなかったんだけど。
個人的にはいわゆる「生き方」系や「啓蒙」系の本はうんざりしているので、あまり読まないのだが、振り返っても何故これをアマゾンで買ったのかよくわからない。震災で生き方が変わった的なデータなどには未だに懐疑的で、それっぽい臭いがしたので、反証したかったのかもしれない。
冒頭に調査データが提示され、「他人にかかわって、相手のためになることをしたいと思っている人には、幸せな人が多いのです」とあったのだが、イヤイヤ、それは違うだろうと思った。そういう心に余裕がある人は一定以上の所得がある人で、だから幸せなんだよと。また相関関係と因果関係を取り違えている人がいるやと思ったわけ。
まあ読み進めてみると、後の方で、年収別のデータとかは出てきているので、変な思い込みをしているのではなさそうだというのは判明したのだが。でも年収が上がるにつれ、年取るにつれSQが高くなる傾向があり、予想した結果で別に何か新しい発見があったとは感じない。また全体を通して、今言われると心地よさそうな言葉が溢れていて、今が旬な感じではあった。
自分には新しいことはあまりなかったけど、「何か自分にもできることがないか。そう思いながら、でもどうしていいか分らないという人にとって、本書は意味のある他者への貢献を考える、一つの材料になるのではないか」という前書きの通りで、そういう関心を持っている方にお勧めしたい。
<目次>
第1章:幸せの秘密はSQにあり
第2章:曲がり角にきた「ゆたかな社会」
第3章:社会はこうして再生する
第4章:SQ社会の未来像
発行:ディスカバー・トゥエンティワン
著者:鈴木謙介
定価:1,500円+税
約250ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた

noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
まあもう「進化論」はいいんだけど。それは置いておいて、インフラからメディア、コンテンツ、ソーシャル、教育と幅広いテーマで最近のメディア周りの流行りを一望するにはもってこいの本だ。
あまりにも取り上げるテーマが広範囲で、雑多な印象をもった。それもその通りで、まえがきにもあるが、本書はラジオ番組を書籍化したものだ。「クロストーク」という対談形式のものも、各Partに散らばっており、10人の著名人との対談も収録されている。
確かにラジオで1回だけ流すにはもったいない内容ではあるので、ごった煮的ではあるが、メディア周りの今ホットな事柄を再確認するにはよいだろう。個人的にはなるほどと思った部分もあるが、付箋はほとんど付かなかった。
<目次>
Part 1:All Digital 通信と放送の融合
Part 2:Social Media 誰もが主役に
Part 3:Signage & Cloud どこでもメディア
Part 4:Digital Textbook & Teaching 電子教科書
Part 5:Cool Japan クールジャパン
発行:ディスカバー・トゥエンティワン
著者:中村伊知哉
定価:1,000円+税
約250ページ
関連リンク:
書評ページをまとめた

noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 11ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
ウェブアナリスト 宏美のブログ。WebAnalyticsの3Cデータと関連情報を提供。一つはcompetitor、市場マクロデータや競合データ。一つはcompany、自社のアクセス解析データ。最後はcustomer、ユーザー行動データ。数値の一人歩きをさせたくないので、詳しくは原典と各調査方法を確認のこと。Unknownnoreply@blogger.comBlogger9007125
Insight for WebAnalytics フィード を購読