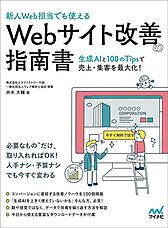14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html■ 「アトリビューション」分析への姿勢は「深入りしない」が結論ですアクセス解析イニシアチブのような団体を運営していると、何か集中的に勉強したくなった時に、すぐにセミナーを開催してみたり、分科会活動をしてみたりということが能動的に素早くできるという素晴らしさがあります。今年後半に本当に集中的に話を伺ってきたのが、「アトリビューション」です。7月下旬から12月上旬まで、ほぼ隔週で分科会という形で開催し9回で終了となりそうです。この頻度で我ながらよくやりました。改めて「アトリビューション」とは、広告の間接効果の貢献度をどう「配分」するかみたいな話で、広告の間接効果を評価し、適切な広告活動の役に立てようということです。少し拡大解釈して、コンテンツ接触も含めたセッションを跨いだ集計全般まで私の場合は含めています。で、その「アトリビューション」分析に対してどう今後取り組むべきかという結論なのですが、タイトルにも示した通りで、今のところ深入りしない方が良さそうだということです。もちろんこれはサイトの規模、集客施策に対する投資額などによって事情は違ってきますが、僕が個人的にこの分野に取り組み始めるのは難しいと判断しましたという意味です。8月29日のメルマガにも書いてある通り、「簡単ではなさそうだ」という直感に間違いはなかったようです。仮説立案、試行錯誤、大量データの処理といったハードルを同時並行にこなしていくには、それなりのチームで分析しないと手に負えないと思いますし、そこに明確にテスト的に投資して頂けれるお客さんがゴロゴロしているとも思えません。しかし、現在どこまで出来ているのか、どういう世界が待っているのか、自分がこれに取り組むにあたっては将来どういう立ち位置にいるべきかということを考える上で、やはり多くの方のお話を聴いて、質問して、大変参考になったことは言うまでもありません。9回の勉強会は大きな収穫でした。
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html■ 結論を急ぎ過ぎて、自分で考えられない人間にならないようにしたい今デジタルハリウッド大学院で、2011年後期のアクセス解析実践の授業が大詰めなのですが、今年は人数が非常に多く留学生も多いので、受講生のレベルのバラつきも大きいです。まあそれは仕方がないのですが、私の授業では結構高い頻度で簡単な質問や課題をやってもらいます。今回気になったのは、その課題に対して取り組む姿勢についてです。私の配布資料は、問題と答えが同じページに見えないように、資料の並びをわざわざプレゼンの順とは変えていたり工夫を凝らしているので、授業の前にそれを見て予習したり、演習時にページをめくらないように予め指導しています。しかしそれを知っていながら、課題を出した後にすぐに答えのページを見ている生徒が居たり、すぐに答えを導くのに直結するような質問を投げかけてくる生徒がいます。正解を急ぐ人が多くいるのです。デジハリの大学院生は、殆どが社会人で社会経験のある人のはずなので、大学院での学習は、まさに「考える訓練」をさらに積むことにあって、正解を聞きに来ている筈ではないと思うのですが、そういう人はいます。アクセス解析でも同じで、正解をすぐに答えられるのは、特定のツールの使い方や、そのツールでどこまでわかるかといった仕様やテクニックまでです。それ以外に関しては、正解なんてありません。サイトによって事情が違うので、それにマッチした分析手法はこれがいいでしょうという推奨はできますが、それが本当に100%正解かどうかはサイト運営者自身が自分で試行さくごを続け、その時どきに応じた最適解を模索するしかないと思います。しかしいろんな活動をしていると、突然質問(しかも正解を求める)に来る方がいらしゃいます。忙しい担当者の立場では、今解決しなければならない問題が山積しているのだろうなということは理解できるのですが、周りの人に答えを求め過ぎて自分で何も考えない人になっていないかどうかが気になります。そういう質問に対する私の答えは決まっています。「それにはこれこれこういった考え方をしてみて下さい。ただし、あなたのサイトや事業について私は詳しく理解していませんから、この原則からあなた自身で判断したり、テストしたりしてみて下さい」と。もちろん個別コンサルでお金を頂くようなケースは、一緒に一生懸命様々なことを考えていくことにします。その場合でも「一緒」に考えてもらったり、教えてもらったりします。私はその事業固有の事情を知らないのですから、自分一人で、独り善がりの妄想や仮説で「かってに解析!」のようなことはしません。
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
結論から言うと、個人的には付箋がついたのは1ヶ所だけだった。「業務統計」と「調査統計」は違うものだというくだりだけ。犯罪統計は業務統計であるので気をつけろということ。つまり何を犯罪と定義するかは、業務上での恣意的な括りで決まるものなので、第3者的統計とは違うというものだ。個人的には、どんな統計だって目的があるので、そんな区分けをしなくても、私の中では統計における「恣意性」なんていうのは初めからあると思っているが、なるほどとは思った。本書は様々なデータを「相関図」というグラフの種類に絞って、統計データを説明しているユニークな本だ。私は別に何かをこれで特別得たということはないが、いろんなデータに興味がある人は一読の価値はあるだろう。相関図での落とし穴についてはきちんと書いてある。単なる相関なのか、因果関係なのかが「相関図」では特定できないというのが最大の問題点で、殆どが因果関係で説明してしまいがちであることには注意したい。そういった頭の体操をしたい方にもお薦めだろう。あとは本書を読んで欲しいが、相関係数、外れ値、回帰線といったような項目が相関図では問題になってくるが、この辺りの話題も豊富な実例を通して、すんなり理解が進むのではないだろうか。<目次>第1章:典型的な相関図第2章:散布図によるグルーピング第3章:散布図のさまざまな使い方第4章:バラツキを比較する第5章:相関度の高くない相関図第6章:相関を掘り下げる第7章:男女の相関第8章:反転する相関第9章:片相関第10章:意味のある無相関第11章:相関からはずれたものに注目する第12章:時代とともに移り変わる相関発行:技術評論社著者:本川 裕定価:1,580+税約250ページ関連リンク:
書評ページをまとめた
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
ウェブアナリスト 宏美のブログ。WebAnalyticsの3Cデータと関連情報を提供。一つはcompetitor、市場マクロデータや競合データ。一つはcompany、自社のアクセス解析データ。最後はcustomer、ユーザー行動データ。数値の一人歩きをさせたくないので、詳しくは原典と各調査方法を確認のこと。Unknownnoreply@blogger.comBlogger9007125
Insight for WebAnalytics フィード を購読