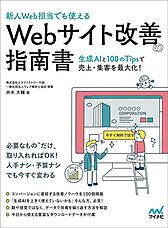13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html■ データはシンプルにトレンドで見るのがよい2012年5月30日に総務省の平成23年通信利用動向調査の結果が発表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000040.htmlインターネット普及率などは飽和状態で変化も乏しくそれほど面白いデータにはなっていませんが、地域別、性年齢別などの軸で違いをみると俄然面白みのあるデータになってきます。またスマートフォンやタブレットなどの新しいデバイスについても昨年から選択肢に加わったようです。時代の変化に合わせながらも継続性を保持するような工夫は調査で必要なことです。デバイスの世帯普及率のデータでは、10年以上のデータを折れ線表示しています。パソコンがこの2年で普及率が少し落ちていたりしているのは、サンプリングの変化などによるテクニカルな問題なのか、スマートフォン利用の増加でPCの代替利用が進んでいるのか、詳しく見てないので判断できておりません。なぜならFAXも落ちてきているからです。もう一つ下記の注目データで★を付けたトレンドデータに、モニターの画面解像度の変化というものがあります。StatCounterのデータは信用していないので絶対値はあまり参考にしませんが、大解像度化の傾向が一貫して進んでいるということは頷けます。装飾をいっぱい施したインフォグラフィックスが流行っているようですが、バックは白で縦軸がゼロから始まるシンプルな折れ線グラフが変化を見たい場合では一番です。グラフはなるべく一つのことを語らせることをお薦めしたいと思います。
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html■ 監視カメラ肯定派ですか否定派ですか?最近はテレビで事件に関係して監視カメラで撮った画像が紹介されることが多いですが、犯罪捜査にどのくらい役に立っているのでしょう。本当の事は関係者ではありませんからわかりませんが、システム全体の性能向上によって有効活用できている気がします。昔は再生した動画を人が見ていたようですが、今や犯人の画像などを登録しておけば、瞬時に膨大な時間の動画を一瞬でパターン認識でき、候補を抽出するそうです。このようにデータを収集する技術の進歩は留まるところを知りません。大変役に立つ一方で、やはり使い方や運用を間違えると、プライバシーの侵害に発展します。個人的には国民背番号制や監視カメラなどは肯定派です。そのメリットの方が著しく高いと考えているからです。国民背番号制で税金の徴収漏れとかを防ぐようなことで、税徴収がかなり増えたりする効果があると考えているからです(もちろんこれは幻想かもしれません)。その時のデメリットをどう考えるかです。結局はバランスなのですから。例えば芸能人の国民年金加入状況などを管轄役所の職員が見て、ネットに流出なんてことは、旧態然のシステムの今でも起こる訳で、個人的にはその程度(と言っては失礼ですが)のリスクは大した話ではないと。秋葉原では例の事件が起きた後に監視カメラの設置が増えたといったような話を聞いたことがありますが、その映像を誰が見ることを許可するのかは、何らかのルールがあるようです。結局は関係者がまずは自主的に常識識を持って考えることが大事でしょう。マーケティングデータも同じだと思います。オンラインのデータだけでなく様々なデータを連携するようなことは技術的にも運用的にも現実のものになってきている時代になりました。どのようなメリット・デメリットがあるのか、悪用されると何が起こるのか、そういったことを予め考えてどう運用していくべきか、我々自身が自分事として考えておきたい問題です。単純に感情的なよい/悪いで平行線の喧嘩をするのではなく、どうバランスを持つのかをきちんと議論することが重要だと思います。
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html■ Google アナリティクス本は7月には出したいGoogle アナリティクス新バージョンのマニュアル本を執筆中ですが、途中でヘビーな仕事が入ってきたりで、思うようには進んでいませんが、7月には完成しそうな気がしてきました。販売中止にした「おしえて! Google Analytics」に収録していた、データ収集の仕組みや指標の定義、タグのカスタマイズなども情報更新する予定です。基礎を正しく理解してないまま利用されている方も多いようなので、活用以前に大事なこともしっかり書いてあります。まあマニュアル本なので、活用方法は各種良書に任せます。操作とか指標とか基本的なことだけでも大変なボリュームになります。画面のキャプチャーも原寸大かなるべく大きくしているので、現在600ページ程度になっています。画面キャプチャーは全て一旦取ってあるので、出版する時までに大幅な変更とかがないことを願うばかりです。先週レポート画面の指標が全面的に英語になっていたので、日本語表記にも変更があったのではないかと戦々恐々としております。まあ完成してもいないのに、どんな値付けで、どんなバリエーションで出そうかという妄想だけは膨らんでいますが、乞うご期待ということで。
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
定期メルマガの巻頭コラムのアーカイブです。メルマガの登録はこちら↓からどうぞ。http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html■ 安宅さんも言ってた「一次情報にあたれ」と先週行われた「アクセス解析サミット」で基調講演をして頂いた安宅さん(ヤフー執行役員)の話は非常にテンポ早く、何しろ話が痛快でした。抽象論なのですが、本質的なことは多くの聴衆の心を鷲掴みにしたようです。先週の巻頭コラムのタイトルが「調査データはソース(発表元)にあたれ」だったのですが、図らずも安宅さんのプレゼンの中の一つにも「一次情報に触れろ」といった話がありました。メディアが適当に切り取った表層的な断片の情報ばかり収集してもゴミだと言い放つ辺りは、基本的に私がよくいう話と近いなあと感じました。彼の著書「イシューからはじめよ」のまえがきでは、MECEやロジックツリー、フレームワークなどといったツールやテクニックの紹介が多い「問題解決」や「思考法」の本とは違い、もっと源流にある原則を書いた本を目指したといったことが書いてあります。イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」
http://www.amazon.co.jp/dp/4862760856どうしても目前の仕事や問題が与えられていると、そもそも論に戻ったりしにくいのですが、そこに僅かでも時間を割くことで、多くの時間を無駄にしなくなるというのは、全くその通りだと思いました。そしてそもそも論に戻ることで、自分自身の仕事が無くなることへの恐怖もないとは言えません。分析の仕事でも、話しをよく伺うと、本当にそれって必要なのかなとか考えさせられるケースも多々あり、サービス提供側の視点からみると、その辺りに関しても考えさせられました。事業者の方に話をする場合、最近は正直に、分析も投資対効果でユーザーは考えるべきであると申し上げています。
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
仕事とはあまり関係ない本をどんどん読んでいくシリーズの第2段。2012/3に亡くなった思想家/詩人/批評家の吉本隆明氏の2006年の本だ。簡単にスパッと切れるような本ではないが、いくつか気になった文章とそれについての意見を書いておく。「時代が下るにつれて精神はだんだんダメになってきたという言い方が、一般論としてはあり得るような気がします。」とあるのだが、少々違うのではないかと思っている。真意は同じなのかもしれないが、人間の本質は道具が進歩してもそれ程急激に進化しないので、相対的に心身ともに時代についていけないということだと思っている。「日常生活では...あるいは家庭の中で何か問題があるかどうか、などといったことと、その人自身がプロとして優れているかどうかということは、区別して考えるべきだと思っています。」というのは凡そ同意できる。人間だれしもが聖人君子なんてことはないから。そして最後のパラグラフ「なにはともあれ、いまは考えなければならない時代です。...いま、行き着くところまできたからこそ、人間とは何かということをもっと根源的に考えてみる必要があるのではないかと思うのです。」は、行き着くところまで来たとは思っていないが、常に考えることは大事だということだろう。何れにしても人生経験の長い人の文章には含蓄がある。<目次>第一章:善悪二元論の限界第二章:批判眼について第三章:本物と贋物第四章:生き方は顔に出る第五章:才能とコンプレックス第六章:今の見方、未来の見方発行:講談社著者:吉本隆明定価:495円+税
約260ページ関連リンク:書評ページをまとめた
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
13 years 7ヶ月 ago
noreply@blogger.com (hiromi ibukuro)
ウェブアナリスト 宏美のブログ。WebAnalyticsの3Cデータと関連情報を提供。一つはcompetitor、市場マクロデータや競合データ。一つはcompany、自社のアクセス解析データ。最後はcustomer、ユーザー行動データ。数値の一人歩きをさせたくないので、詳しくは原典と各調査方法を確認のこと。Unknownnoreply@blogger.comBlogger9007125
Insight for WebAnalytics フィード を購読