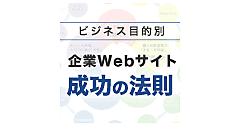成果指針設定の流れ
成果指針設定の流れ
あなたの企業にとってWebサイトが何を成し得るべきか、その位置付けやWebサイトの戦略を明確にしその位置づけに合った目標を成果にする、というところまでお話しました。次に、具体的な測定指標を決めてからの流れをまとめます。ポイントとしては、測定指標に対し成果達成の仮説をたててから効果測定するということです。「何がどうなったら成功」という仮説を定めずに、ログ解析や各データの比較をして、後から成功したとみなすことはあまり意味がありません。
- 測定指標を決める
コールセンター業務改善のために「問い合わせ件数を削減」する - 現状把握(必要に応じて定期観測)
現在の問い合わせの件数や内容傾向の分析 - 数字を評価・検証する
人が説明する必要のない基本的な問い合わせが多く、時間がとられてしまっている - 仮説を立てる
Web上のサポートコンテンツが機能していないのではないか - 仮説に基づき調査をする
サポートコンテンツの有無、訪問者数を確認 - 改善計画を立てる
コンテンツを拡充する、ナビゲーションを改善する - 仮説に基づきた成果数値を算出する
公開1か月後に、月間の問い合わせ件数を10%削減させる - 計画を実施する
コンテンツ制作、サイト構造の改善 - 成果指標の効果測定をする
コンテンツ閲覧回数(アクセス解析)および、問い合わせ件数・内容を測定 - 効果測定結果を社内で共有する
仮説と結果をレポート化する
成果を共有にすることによる効能
記事の冒頭で取り上げた企業Web担当者の嘆きの中に「社内の無関心」というものが挙げられました。これを改善するには、今までお話してきたようなビジネスとしての成果を掲げるのは勿論のことですが、成果の共有を行うことも不可欠です。ビジネスの成果を関係各部署のミッションとシンクロさせることで、以下のような効能があります。
- 興味・関心を示し、Webに関わる業務に積極的になってくれる
- Webに関わる業務が、各部署で「業務」と認められやすくなる
- Webを戦略的に位置付け、計画的に運用・管理することができる
- 予算計画・運用計画が立案しやすくなる
- Webに関わるルール・ガイドライン・業務フローが守られる
- 各部のいろいろな要望を整理できる
成果達成の可否結果を必ず社内で共有することで社内の関心が高まり、結果として関係各部署の協力の基に、より成果を達成できるWebサイトが実現するのです。
今回で第一部は終了です。次回からは第二部として、第一部で取り上げた「目標」を成し得るためのケース別事例と具体的な対策について紹介します。第二部の初回記事では、企業の人事担当者に向けて「必要な人材を獲得するための採用サイト」をテーマを取り上げます。