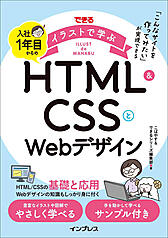Aggregator
Fireworks User Group第三回勉強会が2月5日に開催されます
2012年2月5日(日)14:15-16:00、五反田文化センター 第一会議室にてFireworks User Group第三回勉強会が開催されます。
出演は、丸山 章さん、関口和真さん。参加費は500円です。
掛け算の順序が違うといって×にする教育には考えさせられる [週刊IFWA 2011/12/26]
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ 掛け算の順序が違うといって×にする教育には考えさせられる
「4人に3個ずつミカンを配るとき、ミカンは何個必要?」という問題を計算するとき、「掛け算には順序がある」という理由で、4×3とすると不正解にするという先生がいるらしいです。
掛けられるものと掛けるものがある、だから順序があるということらしいのですが、その説明を受けるとなるほどそういう考え方は間違いではないと思いましたが、考え方のプロセスはそんな画一的ではないだろうとも直感したのでしょうか、大変違和感がありました。
教育の仕方としても、思考のプロセスまで一つの正解を押しつけるのはどうなのだろうという疑問も持ちました。教育の話は、恐らく皆さん誰もが持論を持っていることだろうとは思いますし、これが正解だと言いきれるような世界ではないでしょうけど。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。私の知人にも賛否両論あるようでした。私自身統計とかにはうるさいですし、おかしな数字の解釈には批判する人間ですが、掛け算は3個×4人、4人×3個どちらでもいいと考えます。もちろん3人×4個のように、付ける単位が間違えていたら不正解です。
そんな話を年末考えさせられたのですが、今年は皆さんにとって如何でしたでしょうか。3月の震災も含めて様々なことが起こり、時代はますます早く動いているように感じます。もう数日で今年も終わります。
スピードばかり求められる時代においても、変だなあ/おかしいぞと思ったことに対して、立ち止まって、じっくり考える時間を持つことも大事だと再認識しました。
本件もそういう意味では、自分だったらどういう説明を人にするだろうということを考えさせられたことの一つです。まず自分で考えてから、人の意見を聞く・読むとよいと思います。例えば下記の記事もご覧になってみてください。私がもやもや感じていたことに近いことをきちんと解説してくれています。
文書化能力向上コンサルタントの開米瑞浩氏のブログから。
http://blogs.bizmakoto.jp/kaimai_mizuhiro/entry/3987.html
独自のデザインで見る人を混乱させるユーザーインタフェースの愚 [週刊IFWA 2011/12/19]
http://ibukuro.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html
■ 独自のデザインで見る人を混乱させるユーザーインタフェースの愚
初めて訪問する場所へ出かける時、必ず地図を紙に写して持参することにしています。自分は方向感覚は優れている方だと思っていますが、用意は怠りません。
さて先日のことですが、自分で用意した地図を持ちながら、地下鉄新橋駅改札を出たところで地図を見ました。しかし自分の用意した地図と全く一致しません。3分はその地図を見ていたでしょうか。でも結局その地図が理解できず方向感覚が定まりません。
仕方なく改札の駅員さんに、JR鳥森口改札って一体何番出口から出るのがいいのかを聞いた上で、さらにその地図に戻りました。瞬時に方向感覚は戻りませんでしたが、暫くして謎は解けました。その地図では、なんと上が南南西を向いていたのです。
しかも今居る立ち位置から左右が一致している訳でもなさそうでした。鳥森口というようなヒントになる記述もありません。幾つかの手掛かりで補正することもできなかった訳です。
そう言えば、その地図には人だかりがして、その人達も中々立ち去らずにスマートフォンと見比べている人達が大勢いました。多分皆さんも迷っていたんでしょう。
地図なら基本的に上が北を示すように書くという暗黙のルールがあります。デザインの格好良さなのか、地図の書きやすさなのか、どういう理由なのか判りませんが、南南西が上を向いているこの地図には混乱させられました。
ウェブサイトのユーザビリティなどでも、一般的でない横スクロールだとか、初めて来た人には全く理解のできないユーザーインタフェースを提供しているサイトがたまにありますが、ユーザーはそのサイトの斬新なユーザーインタフェースを学びに来ている訳ではありません。
当たり前のことですが、デザインはユーザーにとって判りやすいことを犠牲にするための独り善がりのものではないと思います。決められたルールやフォーマットの制約の上で、素晴らしいデザインをして欲しいと願っています。
(「デザイン」という広義な言葉使いが自分でも気になりましたが、そのあたりはご容赦下さい。)
フェイスブック広告を支援する無料便利ツール
------------------------------
Free Facebook Marketing Tools
http://www.socialadstool.com/free-tools
Social Ads Tool
http://www.socialadstool.com/
------------------------------
ソーシャルアズツールは、フェイスブック広告の管理画面からは指定できない「Action Spec Targeting」(「Spotifyで音楽を聴いた」などのようなオープングラフのアクションによる広告のターゲティング)にも対応しているようだ。
Google appsの利用時間シェア、Android Marketが35%を占める など
2012/1/27のNielsenのブログから。http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/in-india-google-leads-the-smartphone-app-race/
この1年でEU5カ国でスマートフォンでウェブやアプリ、コンテンツのダウンロードをする人は62%増
2012/1/27のcomScore Data Mineから。http://www.comscoredatamine.com/2012/01/mobile-media-usage-sees-strong-growth-across-eu5/
2011Q4世界のiPhone出荷台数は3,700万台
2012/1/27のCanalysのリリースから。http://www.canalys.com/newsroom/top-smart-phone-vendors-hit-record-volumes-q4
2011世界のスマートフォン出荷、Samsungが9,500万台でトップ
2012/1/26のiSuppliのリリースから。
http://www.isuppli.com/Mobile-and-Wireless-Communications/News/Pages/Apple-Retakes-Smartphone-Lead-in-Q4;Samsung-Grabs-Top-Spot-for-Full-Year-2011.aspx
Abdroidタブレットのアプリ利用回数ベースのシェア、Kindle Fireが36%と急上昇
2012/1/27のFlurry Blogの記事から。http://blog.flurry.com/bid/81151/Amazon-Lights-the-Android-World-on-Fire
2011Q4世界のハンドセット出荷4.1億台の36%の1.5億台がスマートフォン
2012/1/27のABI Researchのリリースから。http://www.abiresearch.com/press/3841-As+China+Eats+Android’s+Tail%2C+Apple+Cuts+Off+its+Head
『プレイス検索SEOで真っ先にやるべき3つの施策』::海外&国内SEO情報ウォッチ
- 『プレイス検索SEOで真っ先にやるべき3つの施策』::海外&国内SEO情報ウォッチ -
Posted on: 海外SEO情報ブログ - SuzukiKenichi.COM
ロッテ 「Fre-1 GRAND PRIX」
CSS Nite back2basic #5「CSS3」が終了しました
2012年1月24日(火)、KDDIウェブコミュニケーションズ セミナールームにてCSS Nite back2basic #5「CSS3」を開催し、70名弱の方にご参加いただきました。

アンケートで次のようなコメントをいただきました。
- シンプルにわかりやすく説明してもらえて良かったです。IE対応、jQueryでしかしてなかったので、filterの使い方を知れて良かったです。
- 今回も“やってみたい”と思える内容でとても有意義でした。自社リニューアルサイトに使っていますが、もう少し生かしたデザインを考えてみようと思いました。HTML5のセクションも見直している所ですが、CSSも同時に考えていきたいと思います。ありがとうございました!
- 覚えればよいプロパティ11個。これを教えていただいてCSS3に取り組むのがやりやすいような気分になりました!勉強して活用したいと思います。
- ついつい簡単にできそうに思ってしまうくらい面白かったです。ありがとうございました。
- CSS3が網羅されていて大変役に立ちました。ありがとうございました。less使ってみたいですね…。
- デザイン的な要素もマークアップ担当に求められる時代になっているのですねー。
- ムダなくスッキリまとめていただいて、これからやっと始めようという私にとっては大変助かりました。ぜひ自分で手を動かして書いてみます。
- ずっと新規の案件を制作する機会がなくて、CSS3に手を付けられずにいましたが、思いの外色々なことができるのだと、今さらながら便利そうな印象をもちました。背景画像を複数設定できるのは助かると思いました。何ができるかを覚えてしまえば、簡単そうなので、どんどん使いたいと思います。
[雑記メモ]血液型論議が盛り上がる理由とプランニングへのヒント
昨日からFacebookで血液型の画像がバズってましたね(下記)。

皆さんのコメントを見ていると、「B型!!(笑)」 「O型だけど当たってる」など反応は様々ながら(まぁ1日2~3個の画像の大シェア大会が始まるのは最近のFacebookの常だけども)皆さんいっせいに食いついてこの血液型コンテンツを消費しています。
その現象を見ながら「なんでこれほど血液型論議は長い間盛り上がり続けるテーマなんだろう」とふと思ったので、移動中の時間を利用して雑記的にまとめてみようというのがこのエントリーの趣旨です。ではにょろりと開始。
<なぜ血液型論議は長い間盛り上がり続けるネタなのか>
●全員が知っていて全員が対象者である
池田さんって結構細かいからA型でしょ!といわれ、「は?血液型って何?性格と関係あんの?」なんて人はいません。科学的根拠は別として「血液型と性格(の関係)」については日本国民のほぼ100%が知っている話題。認知率ほぼ100%。そして、A、B、O、ABのいずれにも当てはまらない人はいない(特殊な例を除き)。「みんな楽しそうだな・・・。でも俺はE型だから話題に入れないや(涙)」なんてことはない。だれもが話題に入ることができる。“世の中ゴト化”されやすいテーマ。
●わかりやすい(潔い)
そもそも多様な人間の性格を4つに分類することなんてとっても難しいわけだけど、そこをあえてバッサリと切り捨てて4つに分類してしまう潔さ。血液型が20種類とかあったらこんなには盛り上がらなかったと思う(「え?池田さんってP型なの?P型の特徴って何だっけ?」みたく)。4つだから「俺(私)は○型でこういう特徴がある」と速やかに “自分ゴト化” しやすい。テレビ番組や雑誌の特集、書籍などでも血液型性格診断や相性占いは取り上げられる本数が多いし、波はありながらも長く取り上げ続けられる普遍的なテーマである。
●ほのかに当たっている
「わかるわかる!」とか「やっぱり○○さんってA型なんだ!」など、ほのかに当たっているところ(正確に言うと血液型別の共通項が積み上げられてできたものだから当たっている風で当然といえば当然。この分野は「血液型気質相関説」とか「血液型人間学」とも呼ばれるらしい。血液型性格分類にあわせてA型の人はA型っぽい性格になっていくという説もある)。そして血液型性格分類は “自分ゴト化” されやすいだけでなく、必ずといって良いほど「他人」の話題におよぶ。「やっぱり○さんってAB型なんだ!」など “トーカブル(Talk-able)” なネタなのだ。つまり飲み会やソーシャルメディアで会話されやすいテーマであるということ。”仲間ゴト化” されやすいのである。
●ほのかに外れている(ツッコミどころ満載)
飲み会とかで、
- 男「そういえば美咲ちゃんって血液型、何型?」
- 女「うふふ。何型に見える?」
- 男「うーん、結構細かいところがあるからA型かな!」
- 女「ブー!実はO型なのでした♪」
- 男「あー!そう言われてみると細かいところもありながら結構大雑把なところもあるからO型かもね!うん、典型的なO型だ!」
と、結局なんでもよかったりする。以前、プランニングには「ツッコマレ・クリエイティブ」が大切って議論があったけど、血液型もまさにそうなのかも。
●意外と深い
血液型と性格の相関や科学的根拠については、実は結構な議論がされています。血液型議論は合コンのライトネタにもなりつつ、Wikipediaの血液型性格分類にもある通り、アカデミアの世界でも活発な議論がされ、科学的根拠から安易に肯定も否定もできないという、実に奥深いテーマなのであります。
ちなみに、「自分ゴト」「仲間ゴト」「世の中ゴト」「他人ゴト」は図にするとこんな感じ。美咲本でも書いたやつです。血液型ネタは「他人ゴト化」されにくいテーマってことですね。
さて、この事実は、マーケティングやコミュニケーション業に携わる人たちにどんな示唆を与えてくれるのか少し想いを巡らせてみました。雑記メモなので荒いです。
<血液型性格分類の人気っぷりからみたプランニングへのヒント>
- 世の中ゴト化されやすいテーマか?(性年代、趣味・嗜好・志向に関わらず誰でもが楽しめる(興味を持つ)テーマか?)
- 一瞬でわかるくらいわかりやすいか?(徹底的にシンプルか? 1秒以内で判断する消費者を自分ゴト化させることができるか?)
- そのネタはトーカブルか?(リアルな場やソーシャルメディアで会話がされやすいテーマか?インセンティブではなく感情が動いて仲間ゴト化されやすい文脈か?)
- 思わずツッコミたくなるポイントがあるか?(ほのかに突っ込まれるレベルが大切でそれ以上になると罵声に変わるので注意が必要)
- 表面上は超シンプルなくせに深く突っ込みたい人には深い仕掛けがあるか? 90%以上の人は表面的な浅い文脈で楽しめつつ、それ以上深く突っ込みたい(楽しみたい)人にはちゃんとそれも用意されていて満足できるか。まぁこれはマストではないかも。
まあこれはターゲットが広い商材に限るかもしれない。耐久消費財、自動車、不動産、嗜好品など、ターゲットやベネフィットが絞られる場合はこの限りではない。また、いわゆるコンテクストプランニングとは別で、その前段階で(当たり前のように)考えるベースみたいなものかな。コンテクストプランニングはこれらのポイントを踏まえ、さらに深堀をしていく作業になると思う。
また、多くの商材は世の中ゴト化も仲間ゴト化も自分ゴト化もされにくい商品・サービスなわけです。トーカブルな商材である可能性も低い。だからこそ、これらの視点からプランニングしなきゃならないということだと思うんです。直球ストレートで勝負しても、誰も打てない、というよりも、その直球に気づいてすらくれない。そこをどうやってバッターボックスに立ってもらうか(アテンションの獲得&自分ゴト化)。そしてバットを振ってもらい(エンゲージしてもらい)、場外ホームランを打ってもらうか(KGIを達成するブランド体験)。さらにホームランの喜びや体験を仲間たちと分かち合ってもらう(共有)。そこがプランナーの腕の見せ所なのです。
なんてことを、昨日のFacebookのバズっぷりを見ていて感じたわけですはい。このエントリー自体がツッコミどころ満載かもしれないと思いつつ、30分ちょっとで書いたブログだから勘弁してってことで強制的に終わり!
2011/12米ウェブサイト利用、1ページ閲覧の平均時間は60秒 など
2012/1/25のNilesenのブログから。http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/december-2011-top-u-s-web-brands/
2011/12米オンライン動画利用、一人平均利用時間は5時間4分
2012/1/25のNilesenのブログから。http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/december-2011-top-u-s-online-video-destinations/
世界のスマートフォン利用、イギリスが45%の普及率でトップ など
2012/1/25のGoogle Mobile Ads Blogから。http://googlemobileads.blogspot.com/2012/01/new-research-global-surge-in-smartphone.html
スマホで有料コンテンツを利用するための条件は「価格」「ユーザーからの評価」
2012/1/26のドコモ・ドットコムのリリースから。
http://www.docomo-com.com/ufile/.pdf
2011Q4世界のタブレット出荷のうちの39%がAndroidOS
2012/1/26のStrategy Analyticsのリリースから。http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&a0=5167
メールマガジンの解約理由は「配信頻度が高すぎる」が41% など
2012/1/26のIMJモバイルのリリースから。http://www.imjmobile.co.jp/news/file/pdf/report/imjm20120126.pdf
2012/1世界のスパムメール比率は69.0%
2012/1/27のSymantecのJanuary 2012 Symantec Intelligence Reportから。http://www.symanteccloud.com/ja/jp/aboutus/general/itemdetails?a=xdpDI8FKOuo=&t=ufmF0TvVPTdu26gS7KOvWg==&inid=
ビューによる自然検索のトラフィック効果は+9% など
ロゼッタストーンとマーケティングメトリックス研が共同実験の結果から。http://markezine.jp/article/detail/15025
米トップ100雑誌に掲載のQRコード、2011Q4は前期対比で18%増
Nellymoserの記事から。
http://www.nellymoser.com/action-codes/qr-codes-and-tags-in-magazine-advertising
2011年度のPC国内出荷実績、4月~12月累計で金額ベースは対前年比92.8% など
2012/1/26のJEITAの統計資料から。http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/pc/2011/
2012年の米モバイル広告、8割増の26.1億ドルに
2012/1/26のeMarketerの記事から。
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008799&R=1008799
電通と民放キー局5社が共同推進するVODサービス名称「もっとTV」に決定 新たにNHKが参加に向け検討中
電通と博報堂の産学連携「MIRAI DESIGN LAB.」、“2030年の社会”に向けた4つの提案を発表
「Ameba」と「ZOZOTOWN」が共同商品をプロデュース 人気有名人ブロガーとのコラボ商品を販売
検索結果によりよいタイトルを
ユーザーにどのようなタイトルを見せるかを決めるために、Google では多くのシグナルを利用しています。もしウェブマスターの方が <title> タグを使っているならば、基本的にはそれをタイトルに用います。しかしどのような検索キーワードに対しても常に <title> タグに書かれているものをそのまま表示してしまうと、ユーザーにとってはそのタイトルは検索キーワードと関連性が低いように見えることもあるかもしれません。そのような場合にそのページが検索キーワードと関連性が高いものであると気づいてもらうため、Google では代わりのタイトルを生成するアルゴリズムを利用することがあります。Google のテストでは、ほとんどの場合においてこれらの代わりのタイトルの方が元のタイトルよりも検索キーワードに対して高い関連性を示しました。また、これらの代わりのタイトルを使用することによりタイトルのクリック率は大幅に向上しており、検索をするユーザーとウェブマスターの皆さんの双方に役立っていました。これが Google が代わりのタイトルを表示する理由の半分です。
もう一方で、HTML 内に何もタイトルがなかったり、そのページを表すようなタイトルがウェブマスターによってつけられていない場合にも代わりのタイトルは表示されます。例えば、タイトルが単純に「ホーム」と名づけられている場合、タイトルはそのページの内容を表してはいません。また、1 つのサイトのページ内でまったく同じ(またはほぼ同じ)タイトルが使われているという問題もよく見られます。最近では、不必要に長かったり読みにくかったりするようなタイトルを簡潔でわかりやすいものに置き換える、という試みも行われています。
よりよいタイトルやメタ ディスクリプションの書き方、代わりのタイトルを生成する時に使われるシグナルに関しての詳しい情報は、「サイトのタイトルと説明の変更」というヘルプ記事をご覧ください。また、Google ではウェブサイトのタイトルが改善できそうなことを発見した場合はウェブマスター ツールの「HTML の候補」という項目でウェブマスターの方にお知らせする取り組みも行っています。こちらはウェブマスター ツールの左側のメニューの「診断」からご覧ください。
この記事に関するコメントや質問は ウェブマスター ヘルプフォーラム までお寄せください。