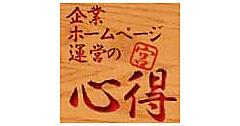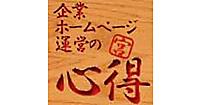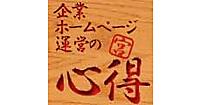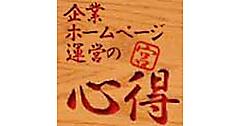iPadでは救えない出版業界。礼賛報道が語らないリスク
iPadが登場し話題を呼んでいます。電子出版への期待も高まりますが新規読者の獲得につながるでしょうか
2010年6月2日 8:00
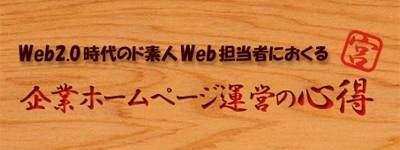
コンテンツは現場にあふれている。会議室で話し合うより職人を呼べ。営業マンと話をさせろ。Web 2.0だ、CGMだ、Ajaxだと騒いでいるのは「インターネット業界」だけ。中小企業の「商売用」ホームページにはそれ以前にもっともっと大切なものがある。企業ホームページの最初の一歩がわからずにボタンを掛け違えているWeb担当者に心得を授ける実践現場主義コラム。
宮脇 睦(有限会社アズモード)
心得其の百六十九
iPadマンセー
上陸の衝撃。日常を変える魅力とは。コレで漫画も読める。手術にも?

2010年5月28日の読売新聞朝刊(首都圏版)のテレビ欄より抜粋した「iPad」に接続された言葉です。教育テレビを除いた6局13番組で「iPad」を見つけ、可能な限りチェックしたニュース番組ではすべて表参道の行列を紹介し、iPadを絶賛するコメントが流されました。同じく新聞全紙が礼賛記事を掲載します。
「iPad」はパソコンからキーボードをなくしたイノベーターとして歴史に刻まれるかもしれません。「キーボード」は織り姫と彦星を別つ、天の川のような「障害物」になります。数十個の無機質な英数字と記号の羅列にアレルギーを起こす人は少なくないのです。ところが「iPad」は画面しかなく、その画面をさわり「動かし」ます。「操作」と意識することもないでしょう。事実上はパソコンであっても、そう感じさせないことによって「パソコンの恩恵」に浴する人が増えるかもしれないからです。
しかし、過熱する「iPad報道」は……というわけで今回は特別寄稿です。
電子書籍というフロンティア
iPad報道でもっともフィーチャーされたのが「電子書籍」で、新しい読者獲得に期待を滲ませます。京極夏彦さんが新刊を電子書籍で発行するとし、「VOGUE」や「GQ JAPAN」といったファッション誌が動画を織りこんだ「電子雑誌」を発売します。私の「マイミク」が言うには、京極夏彦さんの新刊は分厚く重く、読破するのに体力を要するそうです。そこで680g(Wi-Fiモデル)のiPadに期待するといいます。部屋が狭く蔵書ができないので、B5用紙程度の大きさに収まるiPadは魅力だという意見も耳にしました。確かに、わが家には各種雑誌と数紙の新聞による紙の山で埋め尽くされた部屋が大問題になっており、iPadに収納することで訪れる「家庭の平和」に期待しています。
しかし、iPadをもって「新しい読者」を開拓するというのはおかしな話です。
出版業界のカラ騒ぎ
ネットにつながっていればどこにいても雑誌を入手でき、「新しい読者」の獲得に期待できるとするのが理由の1つです。それでは「消費者心理」から考えてみましょう。前述の「VOGUE」「GQ JAPAN」の読者が、iPadを入手して「電子版」を購入する可能性はありますし利便性も高まるでしょう。しかし、ネットに溢れる無料情報に慣れた消費者が、iPadをもったからといって「雑誌に金を払う」でしょうか。消費行動は習慣に支配されますし、通信機能がないWi-FiモデルのiPadでも、本体価格は月々2,220円の24回分割払いです。iPad購入費用を捻出するために、小遣いから「雑誌」が事業仕分けされる可能性は高いと言えるでしょう。もちろん「電子版」とて同じです。一度は「ネタ」として購入するかもしれませんが「ネット利用者と読者層」の違いについての議論が欠けているのです。
なにより電子書籍に「新しい読者」を呼び込む力はないのではないでしょうか。
京極夏彦を読まなければ
京極夏彦ファンは電子書籍を購入するかもしれません。書棚を気にせず蔵書できるiPadがもたらす空間は楽園で、風呂場での読書を毎日の幸せと噛みしめる私自身もiPadに防水機能がつけば飛びつきます。しかし、待ってください。iPadは「活字離れ」まで解決してくれるのでしょうか。
綺麗な液晶画面を「眺め」たとしても、文章を「読む」とは限りません。文字を目で追い、文章として意味を理解する「楽しさ」を理解できないために活字離れがおこります。小銭も切符も不用になった便利な「パスモ」が登場しても、トラックドライバーの日常に変化が訪れなかったように、「デバイス」の変化で「活字離れ」が解決できることはないのです。電子書籍を購入する大半はすでに「活字体験」をしている読者であって「新しい読者」ではないということです。
「新しい読者」という言葉の定義は、電子書籍市場に集う限られた「活字好き」の獲得合戦を意味するのかもしれませんが、どちらにしろ出版業界の市場縮小への打開策にはなりません。
活字離れは悪化する
「動画など紙の雑誌にはない魅力が電子書籍にはある」ことが「新しい読者」を獲得するという主張もあるでしょうが、活字離れの理由の1つは「テレビ」の登場により情報収集に「文章」が不用になったことです。テレビ番組で流される「テロップ」のような短いセンテンスならともかく、一定の文章を読解するには能力と労力が必要です。出版も商売で消費者ニーズにアジャストすることは健全な営業活動ですから、電子書籍にわかりやすい「動画」を求める声が大きくなることは想像に難くありません。その結果、文庫本の読者が「動画」で物語を体験し、iPadで新聞を読むつもりがリンクされた「ニュース映像」に満足し、更なる「活字離れ」がおこる可能性を否定できないのです。
これはコンテンツを作る側の問題ですが、iPadを手放しで礼賛できない理由です。
だからこそ。いま
ある番組ではiPadでのインターネット閲覧をiPhoneと比べて、画面が大きくなり「見やすい」と紹介しますが、それはいわゆる「当社比」の成果を強調する洗濯洗剤のCMと同じであることに「礼賛報道」は触れません。iPadでモデルが着たウエディングドレスの動画を見せ、「着用時」をイメージさせるサービスを便利と褒めたたえますが、ドレスの見栄えには体型という個人差があることはスルーします。また「iPad」をプレゼンテーションに使うという切り口は、主語を東芝の「ダイナブック」に置き換えると懐かしのバブル時代にタイムスリップします。
はっきりいって今の「iPad報道」は異常です。そのなかで、フジテレビの情報番組「とくダネ!」は1点だけみるところがありました。MCの小倉智昭さんが、同番組のコメンテーターも務めるデーブ・スペクターさんが米国発売時に購入したiPadを「不便」だとし、使っていないと暴露したことです。どんな道具にも向き不向きがあるのは当然のこと。踊らされないようにご注意ください。
今回のポイント
デバイスの進化は活字離れを加速させる可能性がある。
報道が過熱した時こそ冷静な視点を。
- 電子書籍『マンガでわかる! 「Web担当者」の基本 Web担当者・三ノ宮純二』
- 企業ホームページ運営の心得の電子書籍
「営業・マーケティング編」「コンテンツ制作・ツール編」発売中! - 『完全! ネット選挙マニュアル』
現場の心得コラムの宮脇氏が執筆した電子書籍がキンドルで2013年6月12日発売! - 『食べログ化する政治』ネット選挙が盛り上がらなかった理由はここにある(2013年8月1日発売)