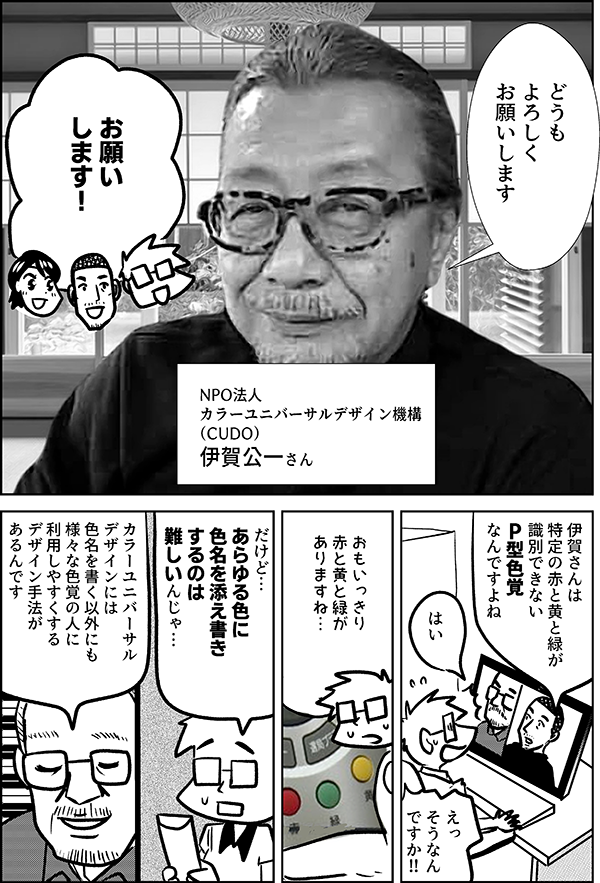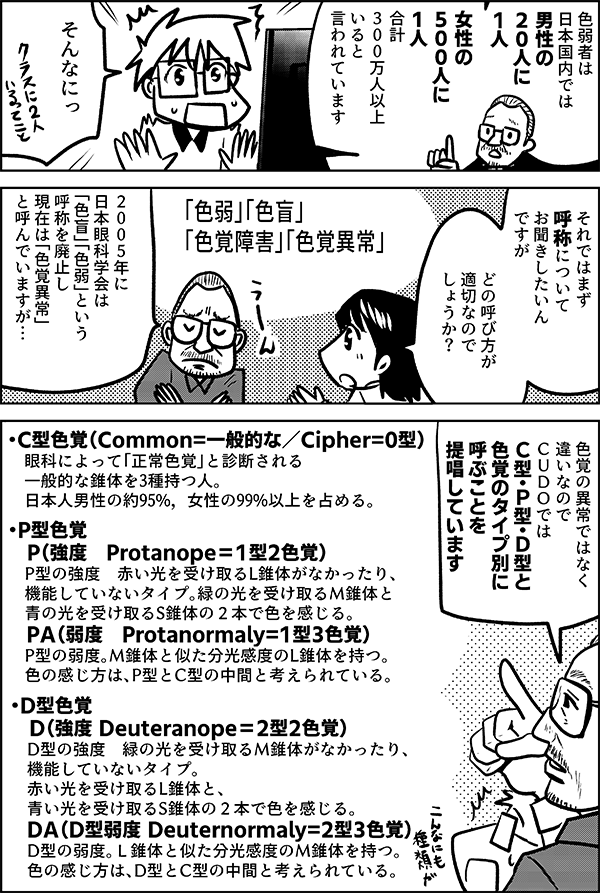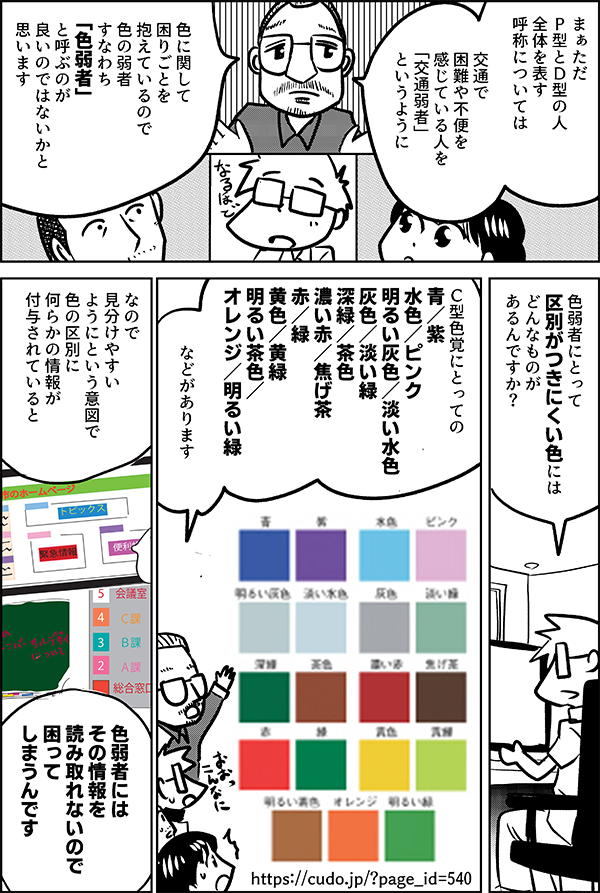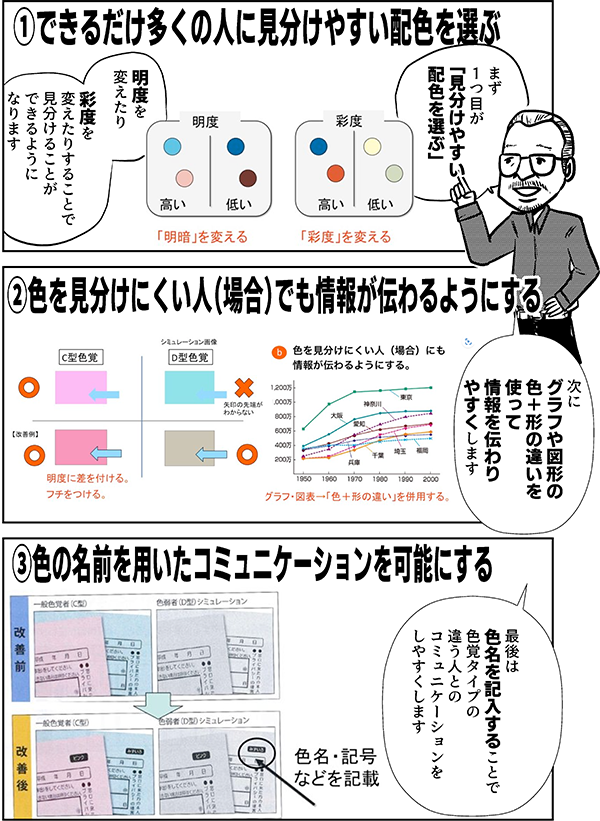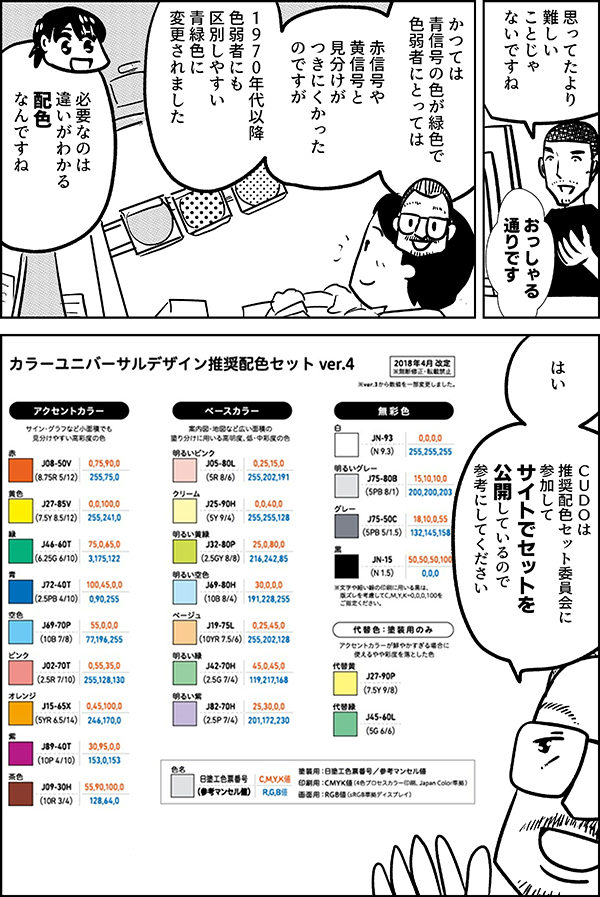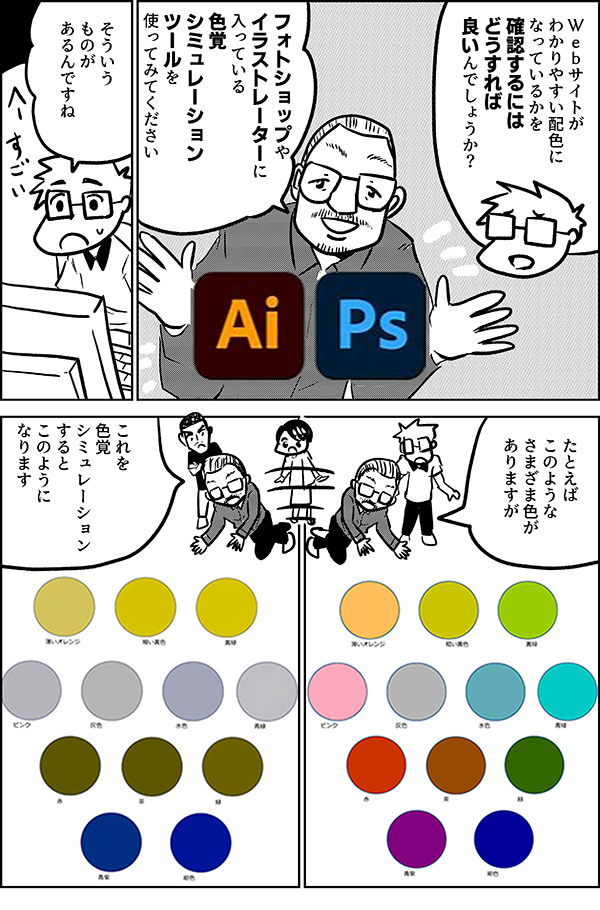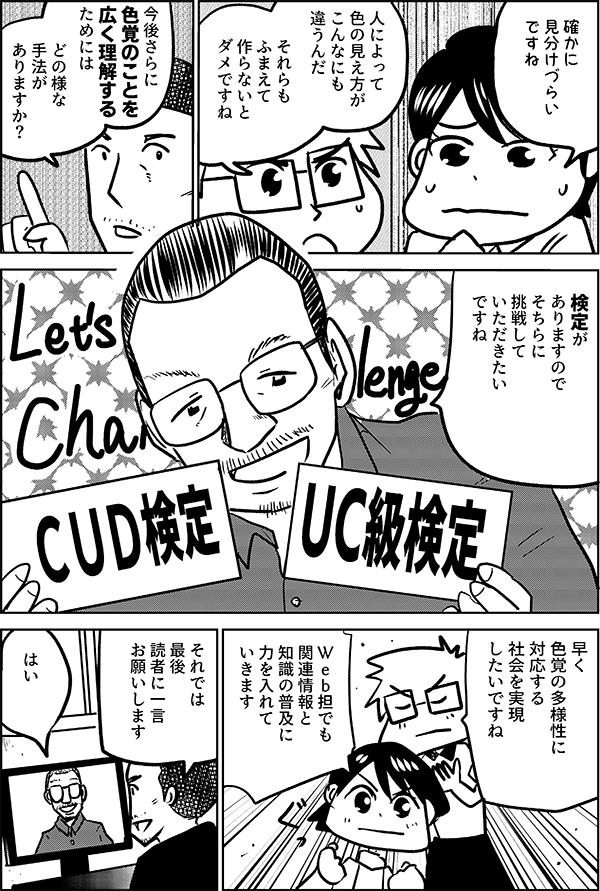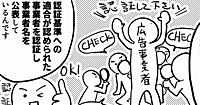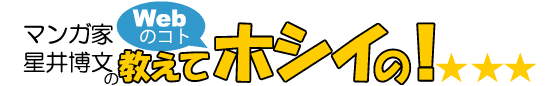
関連記事

伝わるWebサイトをつくる! ユニバーサルデザインの基本と具体的な改善方法
2024年4月11日 7:00

おしゃれな3色の配色パターン組み合わせ:センスのいいビジネス資料に
2023年4月27日 7:00

美味しそうな色の組み合わせ方: 食べ物や飲食店の配色イメージ(第5回)
2017年3月24日 7:00

Gmailにメールが届かなくなる!? 5月中にやるべき対応策をマンガで教えてください!WACUL安藤健作さんに聞いてきた
2024年4月24日 7:00

【勉強・成長のイメージカラー】学校や塾・教育現場で使える配色一覧
2017年4月21日 7:00

マーケターの仕事もグンと楽になる!? Copilotの活用例をマイクロソフトの篠塚祐紀子さんに聞いてきた
2024年3月27日 7:00
バックナンバー
この記事の筆者
星井博文(ほしい・ひろふみ)
漫画家・漫画原作作家。ヤングジャンプにてデビュー。著作に『中京女大レスリ ング部物語「ちゅうじょ」』(実業之日本社)など多数。「グランドジャンプ」にて、『未解決事件 File.02 オウム真理教』などの構成を担当。
筆者の人気記事

Gmailにメールが届かなくなる!? 5月中にやるべき対応策をマンガで教えてください!WACUL安藤健作さんに聞いてきた
2024年4月24日 7:00

どうすれば検索順位が上がるんですか……? SEOについてアイレップの渡辺隆広さんに聞いてきた!
2014年2月19日 9:00

企業Twitterでフォロワーを増やすにはどうすればいいの?/ネット広告代理店オプトに行って聞いてきた
2015年6月9日 7:00
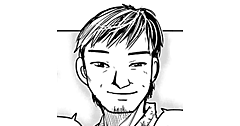
ズバリ、検索で1位になる方法をこっそり教えてください!/グーグルの金谷武明さんに聞いてきた
2015年10月5日 7:00

ヤバいSEO業者ってどうやって見分ければいいの? SEOコンサルタント辻正浩さんと日西愛さんに聞いてきた
2015年1月23日 7:00

Googleアドワーズで成果を出すにはどうすればいいの? リスティング広告のプロ・阿部圭司さんに聞いてきた(前半)
2014年6月5日 10:00