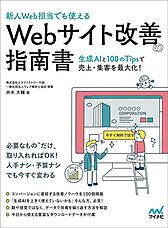14 years 1ヶ月 ago
11月17日(木) 、アップルストア銀座でCSS Nite in Ginza, Vol.60を開催し、150名弱の方にご参加いただきました。

ツイートは下記にまとめました。
次のブログで取り上げていただきました。ありがとうございます。
追記(2011年11月23日):
フォローアップを公開しました。
撮影:飯田昌之

14 years 1ヶ月 ago
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))
14 years 1ヶ月 ago
先日告知のあった「ポストマン」が公開。ソーシャルメディアの友人の住所を知らなくてもカードが送れます。まずはFacebook版。...
14 years 1ヶ月 ago
この度、Google ではウェブ上のコンテンツとその著作者を関連付ける、著作者情報のマークアップに対応いたしました。素晴らしい著作者によるコンテンツを検索結果の中で見つけやすくするために、このデータを使用していこうと考えています。
現在 Google では、ウェブサイト内のコンテンツから著作者情報ページへリンクするマークアップに対応しています。たとえば、多くの記事を書いている The New York Times の記者がいたとします。ウェブマスターは著作者情報をマークアップすることによって、これらの記事を The New York Times の記者ページに関連付けることができます。著作者情報ページは、著作者がどういった人物か説明するものであり、著作者の略歴、写真、書いた記事、その他のリンクなどを含めることができます。
もしあなたがこうした記事等の著作物を掲載したサイトを運営しているなら、ぜひ著作者情報のマークアップについて
ヘルプ記事「著者情報」 をご一読ください。このマークアップは、各検索エンジンやその他のウェブサービスが、ウェブのいたるところに存在する同一の著作者による著作物を識別できるよう、HTML5 (rel=”author”)や XFN (rel=”me”)などの既存の標準技術を利用しています。
schema.org のマイクロデータ (英語)を使用した構造化データのマークアップを既に行っている場合でも、Google は著作者情報として認識します。
Google では、このマークアップを可能な限り簡単に取り入れられるようにしたいと考えています。そのために、The New York Times、The Washington Post、CNET、Entertainment Weekly、The New Yorker などの複数のサイトと協力してページのマークアップに取り組みました。さらに、YouTube や Blogger がホスティングするすべてのコンテンツにもマークアップを追加しました。将来的には、どちらのプラットフォームでもコンテンツの公開時に自動でマークアップが追加されるようになります。
良質なコンテンツは素晴らしい著作者によって生み出されます。Google ではこのマークアップによって、コンテンツの著作者を強調したり、検索結果のランク付けを改良したりできないか、その可能性を模索してまいります。
Posted by Othar Hansson, Software Engineer
Original version: Authorship markup and web search
14 years 1ヶ月 ago
今年に入り、デジタルマーケティング業界におけるアトリビューションマネジメントの... 杉原剛 http://www.atara.co.jp
14 years 1ヶ月 ago
ビルコム株式会社と、韓国のデジタル工-ジ工ンシーのASIANCE Co.,Ltdは11月21日、デジタルマーケテイング事業での業務提携について合意したことを発表…
14 years 1ヶ月 ago
株式会社セレスポは11月11日、2012年3月期第2四半期(2011年4月1日~2011年9月30日)の決算短信を発表した。
【連結経営成績(累計)】
…
14 years 1ヶ月 ago
アキナジスタ株式会社は11月14日、2012年3月期第2四半期(2011年4月1日~2011年9月30日)の決算短信を発表した。
【連結経営成績(累計)】…
14 years 1ヶ月 ago
noreply@blogger.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))
14 years 1ヶ月 ago
14 years 2ヶ月 ago
noreply@blogger.com (Kenji)
14 years 2ヶ月 ago
誰もが思った以上にスマートフォンの普及している現状、「モバイル検索」「モバイルSEO」なんて完全に忘れられた存在になりつつある昨今ですが(モバイル検索エンジンのクオリティ自体も余り変わってないままですし・・・)、米国の話 …
Continue reading →14 years 2ヶ月 ago
Google+がFacebookの対抗馬になりえるか?という議論はGoogle+のリリース時から続いている話題ですが、実は脅威を感じているのはFacebookじゃなくてTwitterじゃないのか?という話もあったりします …
Continue reading →14 years 2ヶ月 ago
noreply@blogger.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))
14 years 2ヶ月 ago
ツイッターの凄いところは、ハッシュタグという画期的な機能により、同じ興味関心を持つ人たちが、一気に集合して、特定のテーマでおしゃべりを始めることができるようになったことではないかと思います。
フェイスブックやミクシィなどと比較すると分かりやすいでしょう。これらのSNSには話題ごとに会議室やスレッドがあり、メンバーがここに参加することで同好の士が集う仕掛けになっています。
これに対してツイッターには会議室のようなものはなく、代わりにそれぞれのツイートをハッシュタグで結びつけることで、特定の話題に限定した情報交換や交流を実現しています。
特に人気のあるハッシュタグは、自分のタイムラインに入ってくるだけでなく、ツイッターへのサイドバーにある「トレンド」という欄に表示され、多くのユーザーの目に触れ、さらに参加者を増やすことになります。
サッカーの国際試合や野球の日本シリーズなど、大きなスポーツイベントでは、必ずこのハッシュタグによる擬似的なコミュニティが発生しています。あとはそのとき放送されているテレビ番組に関することが多いようです。
一方で、自然発生的に作られたタグが、どんどん利用者を巻き込み増殖していくケースもよくあります。特に日本語ハッシュタグの登場が、こうした機能をさらに強化しているようです。
たとえば、こんな感じ。
まるで『Twitter / Search - #よく友達に言われる事晒す』
いわゆる「大喜利」です。 .bbpBox{background:url(http://a2.twimg.com/profile_background_images/88192103/dh-icon-480x480.png) #ffffff;padding:20px;}神原「日本語ハッシュタグの浸透は?」葉村「具体的な数字はいえないんですがスゴイです。大喜利やっているのは日本人だけだと思います」 #onbizThu Oct 13 11:57:11 via Twitter for MacDaiji Hiratahirata
Twitter Japan 株式会社 広告事業統括、葉村真樹氏の発言 『オンラインビジネスセミナー「プラットフォームとしてのTwitter」』より。
現在、企業によるツイッターキャンペーンでは、参加者に同じタグでつぶやいてもらうことで、オンラインイベントとしての盛り上がりを作ろうとしています。
たとえば現在開催中のこの企画ですね。
【お題:その1】ピノコ with ブラック・ジャック大喜利コンテスト goox手塚治虫 地上最大のTEZUKAキャンペーン
この企画はこれで楽しいと思います。
ただあえて今後さらに「その先」を考えるのであれば、自社で仕切る大喜利だけでなく、「突発的に自然発生したコミュニティ」に、企業アカウントも一ユーザーとして積極的に関与したりすると、ツイッターマーケティングもまた新しい段階に入るのではないかと思われます。
ところで、「大喜利」という寄席芸をテレビに持ち込んだ落語界の革命児、立川談志師匠がお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。
news2u
14 years 2ヶ月 ago
noreply@blogger.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))
14 years 2ヶ月 ago
noreply@blogger.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))
14 years 2ヶ月 ago
noreply@blogger.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))
14 years 2ヶ月 ago
noreply@blogger.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))