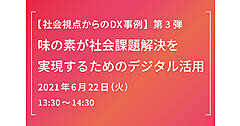また、編集部はこの内容について正確性を保証できません。
Webサイト構築におけるプロジェクト計画書とは、プロジェクトを進めていく上で最初にWebサイト制作担当者からクライアントご担当者様へ提示する資料であり、プロジェクトを計画し、推進していく上でお互いに合意を取るために必要な資料です。
ここではタイトルにある通り「スコープ」の書き方について書きます。
ここで重要なのはクライアントとのスコープの共有であり「プロジェクト内容の共有」です。プロジェクトの「作業」や「成果」を説明するときにお互いがスコープを共有していることで、同じ方向に向かってプロジェクトを推進していくことが可能となります。
プロジェクトのスコープはかなり重要でして、ここで過不足があると後のトラブルとなりやすいです。
プロジェクト全体の整備をして、なにをするべきなのかを前項の目的や課題と解決策などから導き出す必要があります。
ここでは3つのフェーズでのスコープをご紹介します。
また、例で上げた内容でも足りない場合もあるプロジェクトもあれば、余分すぎる場合もあるのであくまで例ということで考えてください。

戦略フェーズ
ヒアリング・RFP確認/オリエンテーション/工数設計/WBS作成/コミュニケーション管理/定例会管理/契約/受注管理/ユーザーテスト/ユーザーシナリオ/ペルソナ作成/CJM作成/KGI・KPI/ロードマップ など
プロジェクトをスタートする場合にはこの戦略フェーズから開始することが基本となるでしょう。具体的な指標などはこちらで設定をしていく、調査などを行った上でKGIやKPIの設定が必要です。プロジェクト計画書はこれらを端的に、且つ分かりやすい方向性を示すためのものですが、戦略フェーズがある程度佳境に差し掛かったら一つの資料としてプロジェクト計画書にまとめ上げるということもあります。