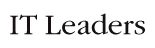『BtoC向けマーケティングオートメーション CCCM入門』 Web担特別公開版

顧客データを分析してセグメントごとにシナリオを設計し、さまざまなチャネルを組み合わせて顧客の行動に応じたコミュニケーションを自動的に行うクロスチャネル・キャンペーン・マネジメントCCCM(シーシーシーエム)。
急成長するマーケティングオートメーション分野のソフトウェアの中でも主にBtoCビジネス向けに高度なパーソナライゼーションを実現するソフトウェアとして注目されています。
本書は、そのCCCMの成り立ちや機能、選定から運用までの実践方法、DMPをはじめとするアドテクノロジーとの連係や主要ベンダー動向まで、使いこなすための知識を網羅したCCCMの教科書です。
はじめに
本書は、広い意味で「マーケティングオートメーション(MA)」と呼ばれるソフトウェアのうち、見込み客管理ではなくチャネルを横断したコミュニケーション実行のために、主にBtoCビジネスで活用される製品を「クロスチャネル・キャンペーン・マネジメント(CCCM)」として分類し、その成り立ちやコンセプト、導入検討の際の注意点や実際の導入・活用方法について解説したものである。日本で導入できる主なCCCMについて簡単に紹介しているほか、海外大手ベンダーの戦略を理解するために本国のキーパーソンへのインタビューも掲載した。
筆者が経営するディレクタスは、CCCMを活用したクロスチャネルOne-to-Oneコミュニケーションの戦略コンサルティングやCCCMの導入・運用支援を行っている。
本書は私たちがCCCMを実際に導入し運用した経験に基づいて、企業のマーケティング担当者でこれから導入を検討しようとしている方や、導入して活用しようとしている方を念頭に置いて執筆した。
日本国内では2014年ごろからCCCMに注目が集まっている。きちんと調査したわけではないが、分かる範囲だけでもかなり速いペースで導入企業が増えてきている。実は日本でも1990年代にはすでに導入が始まっていて歴史があるソフトウェアなのだが、ここにきて「やっと」もしくは「急に」普及が進んでいるのだ。
これは、必ずしも日本だけの現象ではない。欧米に目を向ければここ数年でアメリカの大手ITベンダーが次々と有力なCCCMベンダーを買収し、いまや独立系の大手CCCMベンダーは数少なくなった。そして、それら大手ITベンダーを中心とした勢力が積極的に世界展開を始め、その波が日本にも押し寄せているのだ。そのため、導入検討の対象となるソフトウェアの多くは欧米ベンダーの製品であるはずだ。
実は、これは危険なパターンであり、CRMのときに少し似ている。
マーケティングやデジタルテクノロジーの領域で日本は常にアメリカの後を追いかけているので、デジタルマーケティングの世界においてアメリカではやるものは必ず日本でもはやる。ただ、それがうまくいくかどうかは別である。1990年代のCRMブームのときもアメリカからの流れに乗り多くの会社が雪崩を打って高価なシステムを導入したが、ほとんどの場合、うまく使いこなすことができなかった。というか、まったく使えなかった。これは、いろいろな理由があるが、本来のコンセプトを深く理解しないまま戦略なき導入を進めたことが大きな要因だろう。
CCCMにおいても同じことが起きる可能性は十分ある。そうならないために、CCCMがどんなコンセプトに基づいて何の目的で開発されたソフトウェアなのか、どんな方向に向かおうとしているのかをきちんと理解しておく必要がある。それは、実はマーケティングの大きな潮流の中で必然的に起きている動きだ。その上で、自社の戦略を実現するための道具としてCCCMを使いこなしていただきたい。そして「長い間、本当はやりたかったけどコストの問題や技術的な問題で実現できなかった理想のマーケティングコミュニケーション」を実現するための道具として活用していただきたい。本書がそのために少しでも役立てば幸いである。
2015年7月
岡本 泰治
本書の目次
1.1 CCCMとは何か
1.2 製品カテゴリーとしてのCCCM
1.3 なぜ今CCCMなのか
1.4 企業起点と顧客起点――2種類のOne-to-One
1.5 クロスチャネルコミュニケーション
1.6 顧客体験を提供するためのプラットフォームへ
1.7 CRMの失敗から学ぶこと
第2章 CCCMとアドテクノロジーの連係は何をもたらすのか
2.1 データがもたらす新しいOne-to-Oneの形
2.2 CCCMとアドテクノロジー
2.3 CCCMとDMPの関係
2.4 CCCMとプライベートDMPの融合がもたらす新しいCRMの可能性
第3章 One-to-Oneコミュニケーションチャネルを理解する
3.1 One-to-OneチャネルとOne-to-Manyチャネル
3.2 Eメール
3.3 モバイルアプリ(プッシュ通知)
3.4 メッセージングアプリ
3.5 オフラインチャネル
3.6 新たなチャネルの可能性と動画によるOne-to-One
第4章 実践CCCM ~選定の注意点~
4.1 導入の目的を明確にする
4.2 CCCMのタイプの違いを理解する
4.3 製品選定に当たっての注意点
第5章 実践CCCM ~運用~
5.1 CCCM運用の基本的なプロセス
第6章 日本におけるCCCMベンダーの分類と解説
6.1 本章について
6.2 Salesforce Marketing Cloud(旧ExactTarget Marketing Cloud)
6.3 Oracle B2C Cross-Channel Marketing(旧Responsys)
6.4 IBM Campaign(旧Unica Campaign)
6.5 IBM Silverpop Engage
6.6 Adobe Campaign(旧Neolane)
6.7 SAS Marketing Automation
6.8 Probance Hyper Marketing
6.9 Experian CCMP
6.10 Pitney Bowes Portrait
6.11 smarticA!キャンペーンマネジメント
6.12 Aimstar
6.13 Oracle B2B Cross-Channel Marketing(旧Eloqua)
6.14 Marketo
6.15 HubSpot
6.16 Pardot
第7章 大手ITベンダーインタビュー
7.1 大手ITベンダーに共通するマーケティング分野へのシフトとCCCM
7.2 IBMの戦略
7.3 Adobe Systemsの戦略
7.4 salesforce.comの戦略
7.5 Oracleの戦略